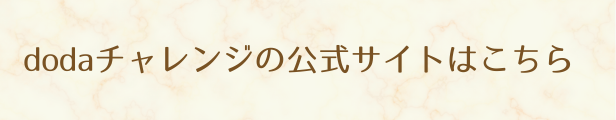dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します
dodaチャレンジは障がい者雇用に特化した転職支援サービスですが、利用を希望しても「求人を紹介できない」と断られるケースがあります。
せっかく登録したのに求人を紹介してもらえなかった場合、「なぜ自分は断られたのか?」と不安になる方もいるかもしれません。
しかし、dodaチャレンジが求職者を断る理由には、いくつかの明確なパターンがあります。
必ずしも「能力が足りない」や「転職が不可能」というわけではなく、希望条件の設定や市場の状況が影響していることが多いのです。
本記事では、dodaチャレンジで求人を紹介してもらえない理由や、断られやすい人の特徴について詳しく解説します。
もし「登録したのに求人が見つからなかった」と感じている方は、原因を知ることで、次の転職活動のステップにつなげることができるかもしれません。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、求職者の希望条件やスキルに合う求人を探した上で、マッチするものがあれば紹介する仕組みになっています。
そのため、希望する条件と市場に出ている求人の条件が合わない場合、紹介できる求人がないと判断されることがあります。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
求人の紹介が難しくなる大きな理由の一つが、希望条件が厳しすぎることです。
例えば、「在宅勤務限定」「フルフレックス勤務」「年収500万円以上」など、条件を細かく設定しすぎると、それに該当する求人の数が大幅に減ってしまいます。
特に、障がい者雇用枠の求人は一般枠と比べてまだ数が少ないため、条件を厳しく設定するとマッチする求人が見つかりにくくなります。
希望条件が多い場合は、どこまで譲れるかを考え、柔軟に調整することが大切です。
例えば、「週に何日かは出社できる」「年収は現状維持でもよい」など、選択肢を広げることで、紹介できる求人の幅が広がる可能性があります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
特定の業界や職種にこだわりすぎると、紹介できる求人が見つからないことがあります。
特に、クリエイティブ系(デザイン、映像制作、イラストレーターなど)やアート系の職種は、もともと求人数が少ない上に、障がい者雇用枠での募集が少ないため、転職が難しくなる傾向があります。
専門職にこだわる場合は、一般の転職サイトやフリーランス向けの仕事紹介サービスなども併用し、幅広く情報を集めることが重要です。
また、dodaチャレンジのキャリアアドバイザーに相談し、関連する職種への転職が可能かどうかも検討するとよいでしょう。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方在住で、通勤可能な範囲が限られている場合、そもそも求人の数が少ないため、紹介できる仕事が見つからないことがあります。
大都市圏に比べて地方の障がい者雇用枠の求人はまだ少なく、特に中小企業では障がい者雇用の受け入れ体制が整っていない場合もあります。
この場合、選択肢を増やすために、フルリモート勤務が可能な求人を探したり、通勤可能な範囲を広げたりすることを検討するとよいでしょう。
最近では、リモートワークを取り入れる企業も増えているため、アドバイザーに相談しながら、在宅勤務が可能な求人を探してもらうのも一つの方法です。
dodaチャレンジで断られる理由の多くは、求職者のスキルや経験ではなく、求人のマッチングに関するものです。
もし紹介できる求人がないと言われた場合は、条件の見直しや他の転職サービスの併用を検討することで、転職のチャンスを広げることができます。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジは、障がい者向けの転職支援サービスですが、すべての求職者がサポート対象となるわけではありません。
場合によっては、登録後の面談を経て「サポート対象外」と判断され、求人の紹介を受けられないことがあります。
これは、dodaチャレンジの基準に基づいており、求職者の状況によっては、他の支援サービスを案内されることもあります。
障がい者手帳を持っていない場合(「障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジが紹介する求人は、基本的に「障がい者雇用枠」のものが中心となっています。
そのため、障がい者手帳を持っていない場合、応募できる求人がほとんどなく、サポートの対象外と判断されることがあります。
ただし、企業によっては「医師の診断書」や「自治体が発行する受給者証」などを提出することで、障がい者雇用枠での応募を受け付けるケースもあります。
手帳を持っていなくても、障がいに対する配慮を必要としている場合は、事前にdodaチャレンジのキャリアアドバイザーに相談し、どのような対応が可能かを確認することをおすすめします。
また、今後障がい者手帳の取得を検討している場合は、取得後に改めて登録し、転職活動を進めるという選択肢もあります。
手帳の取得手続きについては、自治体や医療機関に相談すると詳細を教えてもらえます。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
dodaチャレンジは転職支援サービスのため、基本的に「ある程度の職務経験がある求職者」を対象としています。
そのため、長期間のブランクがあり、ほとんど職務経験がない場合は、企業に紹介できる求人が見つかりにくく、サポートの対象外と判断されることがあります。
特に、過去に一度も就業経験がない場合や、長年働いていない場合は、いきなり転職活動を始めるよりも、まずは就労移行支援などを利用して、職場復帰の準備をする方がスムーズに転職できることがあります。
もしブランクが長い場合でも、これまでの経験やスキルを整理し、キャリアアドバイザーに相談することで、応募できる求人があるかどうかを確認することができます。
また、未経験でも応募可能な職種や、研修制度が充実した企業を探すことで、転職の可能性を広げることができます。
体調が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
dodaチャレンジの求人は、基本的に「すぐに働ける状態の人」を対象としています。
そのため、現在の体調が安定しておらず、就労が難しいと判断された場合は、すぐに転職活動を進めるのではなく、まずは体調を整えることを優先するよう案内されることがあります。
特に、精神障がいや発達障がいがある場合、働く環境によって体調が左右されやすいため、無理に転職活動を進めるよりも、まずは就労移行支援などを利用して、働く準備を整えることが推奨されることがあります。
就労移行支援では、職場でのコミュニケーションや業務の進め方などを学ぶことができ、体調管理をしながら働くためのサポートも受けられます。
また、現在治療中の方は、主治医と相談しながら「どのくらいの勤務時間なら無理なく働けるか」「どのような職場環境が適しているか」を確認し、それに応じた転職活動を進めることが重要です。
もし体調が安定した後に再度転職活動を希望する場合は、そのタイミングでdodaチャレンジに相談すると、適切な求人を紹介してもらえる可能性があります。
このように、dodaチャレンジでは、求職者の状況に応じてサポートの可否が判断されることがあります。
もし登録後に「サポート対象外」と判断された場合でも、他の支援サービスを利用することで、将来的に転職の可能性を広げることができます。
まずは自分の状況を整理し、最適な方法を選択することが大切です。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジのキャリアアドバイザーとの面談は、求職者のスキルや希望条件を把握し、適切な求人を紹介するために行われます。
しかし、面談時の準備不足やコミュニケーションの内容によっては、「求人を紹介できない」と判断されることがあります。
面談は単なる形式的な手続きではなく、転職活動の第一歩となる大切なプロセスです。
そのため、障がいの特性や希望条件について具体的に説明できることが重要になります。
ここでは、面談での印象や準備不足が理由で求人紹介を断られてしまうケースについて解説します。
障がい内容や配慮事項が説明できない
障がい者雇用枠での転職活動では、自分の障がいの特性や、職場で必要な配慮について適切に伝えることが求められます。
企業側は、障がいのある社員が働きやすい環境を整えるために配慮を行いますが、それには求職者自身が「どのような支援があれば働きやすいのか」を明確に説明することが必要です。
例えば、「長時間の立ち仕事が難しい」「定期的に休憩を取る必要がある」「口頭指示よりも書面での指示の方が理解しやすい」など、具体的な配慮事項を伝えられるようにしておくと、アドバイザーも適切な求人を紹介しやすくなります。
逆に、「特に配慮は必要ありません」と伝えてしまうと、実際に働き始めた後に問題が発生しやすくなるため、注意が必要です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
転職活動では、「自分がどんな仕事をしたいのか」を明確にすることが重要です。
dodaチャレンジのキャリアアドバイザーは、求職者の希望に合った求人を紹介するために面談を行いますが、「やりたい仕事がはっきりしていない」「どの業界や職種に興味があるのかわからない」といった状態だと、適切な求人を見つけるのが難しくなります。
特に、「とにかくどこでもいいので紹介してほしい」というスタンスだと、マッチングの精度が下がり、結果的に良い求人を紹介してもらえないことがあります。
職種や業界にこだわらなくても、「自分の得意なこと」「興味があること」「どのような働き方をしたいのか」など、転職の方向性をある程度決めておくと、アドバイザーも求人を提案しやすくなります。
もし明確なビジョンがない場合は、これまでの経験やスキルを振り返りながら、「どのような環境なら自分が活躍できるか」「どのような業務なら興味を持って取り組めるか」を整理しておくとよいでしょう。
職務経歴がうまく伝わらない
dodaチャレンジの面談では、これまでの職務経歴について詳しく聞かれます。
これは、求職者の経験やスキルを把握し、適切な求人を紹介するために必要な情報ですが、職務経歴をうまく伝えられないと、アドバイザーが求職者の強みを理解しづらくなり、マッチする求人を見つけるのが難しくなることがあります。
例えば、「以前の仕事でどのような業務を担当していたか」「どんなスキルを身につけたか」「どのような実績があるか」を具体的に説明できると、アドバイザーが求職者の強みを把握しやすくなります。
特に、ブランクがある場合や短期間の職歴が多い場合は、「その期間にどのようなスキルを磨いたか」「どのような理由で転職を考えているか」を整理しておくことが重要です。
もし職務経歴をうまく伝える自信がない場合は、事前に履歴書や職務経歴書を作成し、それを基に面談を進めるとスムーズに話しやすくなります。
また、アドバイザーに「どのように職務経歴を伝えればよいか」を相談することで、的確なアドバイスをもらうこともできます。
面談での印象や準備不足が原因で求人を紹介してもらえない場合でも、事前の準備をしっかり行うことで改善できるケースが多いです。
自分の障がいの特性や配慮事項を整理し、やりたい仕事の方向性を明確にし、職務経歴を的確に伝えられるよう準備することで、より良い求人を紹介してもらいやすくなります。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応の転職支援サービスですが、地方エリアでは求人の数が限られていることがあります。
特に、大都市圏以外の地域では障がい者雇用枠の求人が少なく、求職者の希望に合う仕事が見つからないことがあるため、求人を紹介できないと判断されるケースがあります。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
地方エリアでは、障がい者雇用を積極的に行っている企業が少なく、そもそも求人の数自体が限られていることがあります。
特に、北海道・東北・四国・九州などのエリアでは、大都市圏に比べて企業の選択肢が少なく、希望する職種や条件に合った求人が見つかりにくい傾向があります。
また、中小企業が多い地域では、障がい者雇用の受け入れ体制が整っていない場合もあり、企業側が求人を出していないケースもあります。
そのため、地方在住の方が転職活動を進める場合は、勤務地の選択肢を広げたり、リモートワーク可能な求人を探したりする工夫が必要になります。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
最近では、リモートワークを導入する企業が増えてきましたが、障がい者雇用枠の求人においては、まだ完全在宅勤務が可能な案件はそれほど多くありません。
特に、地方在住で「完全在宅勤務のみ」を希望する場合、紹介できる求人が極端に少なくなり、結果として「紹介できる求人がない」と判断されることがあります。
リモートワークを希望する場合は、完全在宅にこだわらず、「週に数日出社できる」「状況に応じて出社と在宅を組み合わせられる」など、働き方の選択肢を広げることで、マッチする求人の数を増やせる可能性があります。
また、フリーランスや業務委託契約など、正社員以外の働き方も視野に入れることで、選択肢を広げることも検討してみましょう。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジの登録時に、求職者の情報に不備や虚偽があった場合、信頼性の問題からサポートを受けられなくなることがあります。
特に、障がい者雇用枠の求人は、企業側も求職者の情報を正しく把握した上で採用を検討するため、正確な情報を登録することが非常に重要です。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
dodaチャレンジでは、障がい者雇用枠の求人を紹介するため、基本的に障がい者手帳の取得が必須となります。
手帳をまだ取得していないのに、「取得済み」と登録してしまうと、面談時や企業とのやり取りの際に情報の不一致が発覚し、サポートを受けられなくなる可能性があります。
もし手帳を取得予定であれば、その旨を正直に伝え、取得見込みの時期をアドバイザーに相談することが大切です。
企業によっては、手帳取得予定者でも応募可能な求人があるため、正しい情報を伝えておくことで、適切なサポートを受けやすくなります。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
dodaチャレンジは、すぐに就業可能な求職者を対象とした転職支援サービスです。
そのため、現在の体調が安定しておらず、すぐに働くことが難しい場合は、登録しても求人を紹介してもらえないことがあります。
もし体調が不安定である場合は、無理に転職活動を進めるのではなく、まずは体調を整えたり、就労移行支援などのサポートを受けたりすることが推奨されます。
安定した状態で働けるようになってから再度dodaチャレンジを利用することで、よりスムーズに転職活動を進めることができます。
職歴や経歴に偽りがある場合
転職活動を有利に進めるために、職歴や経歴を実際とは異なる内容で登録することは絶対に避けるべきです。
企業との面接や書類選考の過程で虚偽の内容が発覚すると、選考が進まなくなるだけでなく、dodaチャレンジ自体の利用ができなくなる可能性もあります。
また、職務経歴に関しては、多少の表現の工夫は許容されるものの、実際の業務経験とは異なるスキルや役職を記載すると、入社後の業務で支障をきたす可能性があります。
転職活動では、正直な情報をもとに、自分の強みや経験を正しくアピールすることが大切です。
dodaチャレンジをスムーズに活用するためには、正確な情報を登録し、誠実に転職活動を進めることが重要です。
もし登録情報に誤りがあった場合は、早めに修正し、キャリアアドバイザーに相談することで、適切なサポートを受けられるようにしましょう。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジのサポートを受けながら転職活動を進めても、応募した企業の選考で不採用になってしまうことはあります。
この場合、「dodaチャレンジで断られた」と感じるかもしれませんが、実際には企業の採用基準によるものであり、エージェント側の判断ではありません。
dodaチャレンジは、求職者に適した求人を紹介し、応募書類の作成や面接対策などのサポートを行います。
しかし、最終的に採用の可否を決めるのは企業側であり、選考基準に合わなかった場合は不採用となることがあります。
不採用が続くと、「自分にはチャンスがないのでは」と不安になるかもしれませんが、選考結果に落ち込む前に、どのように改善できるかを考えることが重要です。
不採用は企業の選考基準によるもの
企業が求める人材像と求職者のスキルや経験が合わない場合、選考を通過するのが難しくなることがあります。
特に、障がい者雇用枠の選考では、スキルや職務経験だけでなく、企業の環境や業務内容と求職者の適性がマッチしているかが重視されます。
そのため、「スキルは問題ないが、求職者にとって働きにくい環境になってしまう」と判断されると、不採用になることもあります。
また、企業側の受け入れ体制が整っていない場合や、選考段階で他の応募者がより適していると判断された場合も、不採用となる可能性があります。
このようなケースでは、dodaチャレンジのキャリアアドバイザーに相談し、応募書類や面接のフィードバックをもらうことで、次の応募に向けた対策を立てることができます。
もし不採用が続く場合は、応募する企業の業界や職種を広げる、スキルを見直す、面接の受け答えを改善するなど、対策を講じることで成功率を高めることができます。
転職活動は一度の挑戦で成功するとは限りませんが、アドバイザーのアドバイスを活用しながら、柔軟に対応していくことが大切です。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました
dodaチャレンジを利用しようとしたものの、「求人を紹介できない」と断られてしまったという体験談は少なくありません。
転職活動を始めるにあたって、「どんな求人があるのか知りたい」「まずは相談してみたい」と思って登録したにもかかわらず、サポートを受けられなかった場合、「なぜ自分は断られたのか?」と疑問に感じることもあるでしょう。
しかし、dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった理由には、いくつかの共通点があります。
ここでは、実際の体験談をもとに、どのようなケースでサポートを受けられなかったのかを紹介します。
もし同じような状況に当てはまる場合でも、対策を取ることで転職の可能性を広げることができるため、参考にしてみてください。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。
PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。
紹介できる求人がないと言われてしまいました
この方のケースでは、職歴の内容やスキルの面で、紹介できる求人が限られてしまったことが原因と考えられます。
特に、企業が求めるスキルや経験に合わない場合、dodaチャレンジ側で適切な求人を紹介できないと判断されることがあります。
軽作業の派遣経験がある場合、同じような作業系の仕事や倉庫内作業、清掃業務などの求人は見つかる可能性がありますが、デスクワークや専門職を希望する場合は、スキル不足と判断されることが多いです。
このような場合は、まずスキルアップを図ることが大切です。
例えば、PCを使った事務職を目指す場合、基本的なExcelやWordの操作を学び、簡単な資格(MOSなど)を取得することで、応募できる求人の幅を広げることができます。
また、職業訓練校やハローワークの支援制度を活用して、未経験からでもチャレンジできる職種を探してみるのも一つの方法です。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
このケースでは、体調の安定が確認できなかったため、すぐに就業するのは難しいと判断されたようです。
dodaチャレンジは転職支援サービスであり、基本的には「すぐに働ける人」を対象としています。
そのため、現在の体調が不安定である場合や、過去に短期間での離職が続いている場合は、まずは安定した就労ができる環境を整えるようアドバイスされることがあります。
特に、精神障がいや発達障がいを持つ求職者の場合、職場環境や業務内容によって体調が左右されやすいため、いきなり転職活動を始めるのではなく、まずは就労移行支援などを活用して、安定した働き方を身につけることが推奨されることがあります。
このような場合は、焦らずに自分に合ったサポートを受けることが重要です。
就労移行支援を利用することで、実際の職場を想定した訓練を受けたり、働き方の工夫を学んだりすることができます。
一定期間の訓練を経て就労の準備が整った段階で、再びdodaチャレンジに相談すれば、より良い求人を紹介してもらえる可能性が高まります。
dodaチャレンジで断られる理由はさまざまですが、多くの場合、スキル不足や体調の安定が課題となることが多いです。
しかし、これらの課題を改善することで、転職のチャンスを広げることは十分に可能です。
転職活動が思うように進まない場合でも、他の支援サービスを活用したり、スキルアップに取り組んだりすることで、希望の仕事に近づくことができるでしょう。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。
dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
この方のケースでは、10年以上のブランクがあり、直近の就労経験がないことが理由で求人紹介を受けられなかったようです。
dodaチャレンジは転職支援サービスのため、基本的には「すぐに働ける人」を対象としています。
そのため、長期間のブランクがあり、働く準備が整っていない場合は、まずは就労に向けたステップを踏むことを勧められることがあります。
特に、精神疾患による長期療養後の復職は、体調の安定が重要なポイントになります。
いきなりフルタイム勤務を目指すのではなく、まずは短時間勤務やリハビリ的な就労訓練を通じて、働くリズムを取り戻すことが推奨されることが多いです。
このような場合は、就労移行支援や職業訓練を利用するのが有効な選択肢となります。
就労移行支援では、職場でのコミュニケーションや業務の進め方を学ぶことができ、働くための体力やスキルを身につけることができます。
また、ハローワークの職業訓練を受けることで、新たなスキルを習得し、就職の可能性を高めることもできます。
長期のブランクがある場合でも、段階的に職場復帰の準備を進めることで、最終的には安定した仕事に就くことが可能です。
焦らずに、自分に合った方法で働く準備を整えていくことが大切です。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。
dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
このケースでは、希望する職種の求人が地方では少なかったことが、求人を紹介してもらえなかった理由と考えられます。
dodaチャレンジは全国対応の転職支援サービスですが、障がい者雇用枠の求人は都市部に集中している傾向があり、特に地方では求人の選択肢が限られることがあります。
また、在宅勤務を希望する場合、さらに選択肢が狭まることも影響しています。
最近では、リモートワークを導入する企業が増えてきましたが、障がい者雇用枠の求人では、完全在宅勤務が可能な案件はまだそれほど多くありません。
特に、ライターやデザインなどのクリエイティブ職は、フリーランス向けの仕事が多く、企業の正社員求人としては非常に限られているのが現状です。
このような場合は、転職活動の選択肢を広げることが重要になります。
例えば、以下のような対策を取ることで、希望に合う仕事を見つける可能性を高めることができます。
– 他の転職サイトやクラウドソーシングを活用する
– dodaチャレンジ以外にも、リモートワーク向けの求人を取り扱う転職サイト(リモートビズ、WeWorkRemotelyなど)や、フリーランス向けのクラウドソーシングサービス(ランサーズ、クラウドワークスなど)を活用することで、より多くの選択肢を得ることができます。
– リモートワークOKの企業を探す
– 一部の企業では、地方在住者でもフルリモートで勤務できる障がい者雇用枠の求人を募集しています。
定期的な通勤が不要な企業を探し、直接応募するのも一つの方法です。
– スキルアップをして競争力を高める
– ライターやデザイナーの仕事は、実績やポートフォリオが重要視されるため、実務経験が少ない場合は、スキルアップを図ることで選考通過の可能性を高めることができます。
オンライン講座や専門スクールを活用し、より実践的なスキルを身につけるのも有効です。
地方在住かつ在宅勤務希望という条件は、転職市場では難易度が高くなりますが、選択肢を広げて柔軟に対応することで、希望の働き方に近づくことができます。
もしdodaチャレンジで紹介される求人がなかったとしても、他の方法を模索しながら、自分に合った仕事を探していくことが大切です。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。
dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
この方のケースでは、正社員経験がないことが求人紹介を断られた理由と考えられます。
dodaチャレンジが扱う求人の多くは正社員雇用を前提としているため、企業側が「安定して働けるかどうか」を重視する傾向があります。
そのため、アルバイトや短期派遣のみの経験だと、正社員求人の紹介が難しくなることがあります。
ただし、未経験から正社員を目指す方法がないわけではありません。
例えば、紹介予定派遣の求人を探すことで、まずは派遣社員として経験を積み、企業側の評価が良ければ正社員登用される可能性があります。
また、契約社員やパートからスタートして、正社員登用のある企業を選ぶというのも一つの方法です。
さらに、職歴の書き方を工夫することで、アルバイトや派遣の経験を活かせるケースもあります。
例えば、「アルバイトとして○年間継続して勤務した」「接客や事務のスキルを活かした業務を担当した」といった具体的な実績を伝えることで、企業側の評価が変わることもあります。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。
『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
この方の場合、希望条件が厳しすぎることが求人紹介を受けられなかった理由と考えられます。
特に、完全在宅・週3勤務・時短・年収300万円以上・事務職といった条件をすべて満たす求人は、障がい者雇用枠でも非常に少ないため、dodaチャレンジ側でマッチする求人を見つけるのが難しかったと考えられます。
このような場合、希望条件の優先順位を決めて、譲れる部分を調整することで、紹介できる求人の幅を広げることができます。
例えば、「完全在宅」よりも「週1〜2回の出社は可能」に変更したり、「年収300万円以上」よりも「250万円程度からスタート」にすることで、選択肢が広がる可能性があります。
また、リモートワークを希望する場合は、dodaチャレンジだけでなく、リモートワーク専門の転職サイトや、クラウドソーシングなどを活用するのも一つの方法です。
特に、事務職のリモートワークは企業によって求人の扱いが異なるため、複数の転職サービスを利用することが有効です。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。
dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
dodaチャレンジでは、基本的に障がい者手帳を持っていることが求人紹介の条件となっています。
そのため、手帳をまだ取得していない場合、紹介できる求人がないと判断されることがあります。
ただし、一部の企業では、医師の診断書や自治体の発行する受給者証などを提出することで、障がい者雇用枠での応募が可能なケースもあります。
まずは、dodaチャレンジのキャリアアドバイザーに相談し、手帳取得予定であることを伝えることで、対応できる求人があるか確認してみるとよいでしょう。
また、障がい者手帳の取得手続きは自治体によって異なるため、役所やハローワークで事前に相談し、手続きにかかる期間や必要書類を確認しておくことが重要です。
手帳を取得した後に改めて登録することで、スムーズに転職活動を進められる可能性があります。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。
『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
このケースでは、未経験でのITエンジニア職への転職が難しいことが、求人紹介を断られた理由と考えられます。
dodaチャレンジが扱う求人の多くは、即戦力を求める企業が多いため、未経験の方には紹介できる求人が少なくなってしまう傾向があります。
しかし、未経験からITエンジニア職を目指す方法がないわけではありません。
以下の方法を検討することで、転職の可能性を高めることができます。
– プログラミングスクールやオンライン学習を活用する
– Progate、ドットインストール、Udemyなどのオンライン学習サービスを利用し、基礎的なスキルを習得する。
– 無料または低価格で学べるプログラミングスクールを活用し、ポートフォリオを作成する。
– 未経験OKの求人を探す
– ITエンジニア職の中には、研修制度が充実している企業や、未経験から始められるインターンシップなどもあるため、一般的な転職サイトやハローワークを活用して未経験可の求人を探してみる。
– クラウドソーシングで実績を作る
– クラウドワークスやランサーズで、小規模な案件を受注し、実際にプログラミングの経験を積むことで、転職活動の際に「実務経験あり」とアピールできるようにする。
未経験からITエンジニア職を目指す場合、まずは基礎的なスキルを身につけ、ポートフォリオを作成することが重要になります。
dodaチャレンジで紹介が難しい場合でも、スキルアップをしながら他の方法を模索することで、希望する職種に近づくことができます。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。
短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
この方のケースでは、短時間勤務かつ在宅勤務という条件が厳しかったことが、求人紹介を受けられなかった理由と考えられます。
dodaチャレンジでは全国対応の求人を扱っていますが、完全在宅かつ短時間勤務の障がい者雇用枠の求人はまだ少ないのが現状です。
最近では、リモートワークを導入する企業が増えてきたものの、多くの企業では「完全在宅勤務」ではなく「一部出社が必要」「フルタイム勤務が基本」といった条件を設けています。
そのため、「短時間の在宅勤務のみ」という条件では、紹介できる求人が極めて限られてしまいます。
このような場合、選択肢を増やすために、以下の方法を検討してみるとよいでしょう。
– 週3〜4日の勤務や、一部出社も可能な求人を探す
– 週5勤務が難しい場合でも、週3〜4日勤務や、在宅と出社を組み合わせた働き方を検討することで、求人の幅が広がる可能性があります。
– クラウドソーシングや業務委託案件を活用する
– 完全在宅かつ短時間勤務を希望する場合、企業の正社員・契約社員求人ではなく、フリーランス向けの仕事を探すのも一つの方法です。
クラウドワークスやランサーズなどのサイトを活用することで、ライティング・データ入力・事務作業などの案件を見つけることができます。
– 企業の「障がい者雇用」だけでなく、一般雇用も検討する
– 障がい者雇用枠は、フルタイム勤務を前提とする求人が多いため、一般雇用の中から在宅ワークが可能な求人を探してみると、新たな選択肢が見つかるかもしれません。
完全在宅勤務や短時間勤務の求人は、まだまだ限られていますが、求人の探し方や働き方の選択肢を広げることで、希望に合う仕事を見つけられる可能性があります。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。
dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
このケースでは、障がい者雇用枠で管理職や高年収の求人を希望したことが、求人紹介を受けられなかった理由と考えられます。
一般的に、障がい者雇用枠の求人は、事務職や軽作業などが多く、管理職クラスのポジションは少ない傾向にあります。
特に、年収600万円以上となると、障がい者雇用枠の中ではかなり希少な求人となり、該当する案件を紹介するのが難しくなります。
障がい者雇用枠で管理職を目指す場合、以下の点を考慮することで、転職の可能性を広げることができます。
– 一般枠の管理職求人も視野に入れる
– 障がい者雇用枠では管理職の求人が少ないため、一般枠で管理職ポジションを狙うのも一つの方法です。
企業によっては、合理的配慮を受けながら一般枠で働くことが可能な場合もあります。
– 障がい者雇用の中でも、専門職や経験を活かせる職種を探す
– 一般事務職ではなく、これまでの経験を活かせる専門職(経理、マーケティング、エンジニアなど)の求人を探すことで、比較的高年収のポジションに就く可能性があります。
– 年収やポジションの条件を少し緩和する
– いきなり600万円以上の年収を求めるのではなく、500万円程度からスタートし、昇給やキャリアアップを目指すことで、長期的に希望の年収に近づける可能性があります。
障がい者雇用枠の管理職ポジションは少ないものの、専門職としての経験を活かす、または一般枠の管理職ポジションを狙うといった選択肢を考えることで、転職の可能性を広げることができます。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します
dodaチャレンジで「紹介できる求人がありません」と断られてしまった場合でも、転職のチャンスが完全になくなったわけではありません。
断られる理由にはさまざまな要因がありますが、多くの場合、スキル不足や職歴不足、希望条件の厳しさが影響していることが多いです。
しかし、スキルを磨いたり、働き方の選択肢を広げたりすることで、再び求人を紹介してもらえる可能性は十分にあります。
本記事では、dodaチャレンジで断られたときに取るべき対策について詳しく紹介していきます。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
dodaチャレンジで求人紹介を断られる理由の一つに、「スキルや職歴が不足していること」が挙げられます。
特に、短期間のアルバイト経験のみで正社員経験がない場合や、PCスキルがほとんどない場合は、企業側から「即戦力として働くのが難しい」と判断されることがあります。
このような場合でも、適切な対策を取ることで、転職のチャンスを広げることができます。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
職歴が浅い方や、PCスキルに自信がない方は、ハローワークが提供する職業訓練(公共職業訓練・求職者支援訓練)を活用するのがおすすめです。
これらの訓練では、WordやExcelなどの基本的なPCスキルや、事務職に必要なデータ入力スキルなどを無料または低額で学ぶことができます。
また、職業訓練には、事務系だけでなく、IT・Webデザイン・経理・介護などさまざまなコースがあり、自分の興味や適性に合ったスキルを身につけることが可能です。
スキルを身につけた上でdodaチャレンジに再登録すれば、より良い求人を紹介してもらえる可能性が高まります。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
職歴が浅く、ビジネス経験に自信がない方は、就労移行支援を活用するのも有効な方法です。
就労移行支援では、実際の職場を想定した実践的なトレーニングを受けることができ、以下のようなスキルを身につけることができます。
– ビジネスマナー(報連相の仕方、メールの書き方、名刺交換など)
– PCスキル(Excel・Word・PowerPoint・データ入力など)
– 職場でのコミュニケーション(チームでの作業や会議の参加方法など)
– メンタルサポート(ストレス管理や自己理解を深める研修など)
また、就労移行支援を通じて企業実習の機会が得られることもあり、実務経験を積んでから転職活動を行うことで、より良い条件の求人を見つけやすくなります。
dodaチャレンジで求人紹介を受けられなかった場合は、まず就労移行支援を活用してスキルアップを図るのも一つの方法です。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
PCスキルに自信がない場合は、資格を取得することで、転職活動を有利に進めることができます。
特に、以下のような資格は、事務職や経理職などの求人を探す際に役立ちます。
– MOS(Microsoft Office Specialist):Word・Excelの基本操作を証明できる資格。
事務職やデータ入力の仕事を希望する場合に有利。
– 日商簿記3級:経理職や総務職を目指す場合に有利。
数字に強いことをアピールできる。
– ITパスポート:IT業界の基本知識を証明できる資格。
未経験からIT職種にチャレンジする際の第一歩として役立つ。
資格を取得することで、求人に応募できる幅が広がり、企業側にも「学習意欲がある」「一定のスキルを持っている」と評価されるため、転職成功の確率を高めることができます。
スキル不足や職歴不足で求人紹介を断られた場合でも、ハローワークの職業訓練や就労移行支援を活用したり、資格取得に取り組んだりすることで、状況を改善することが可能です。
転職を諦めずに、スキルアップを図りながら、もう一度チャンスを広げていきましょう。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について
長期間のブランクがある場合、dodaチャレンジでの求人紹介が難しくなることがあります。
特に、数年以上の離職期間があると、企業側が「安定して働けるかどうか」を懸念し、マッチする求人が見つからないケースがあります。
また、「働くことに対する不安が強い」「すぐにフルタイム勤務が難しい」といった理由から、まずは就労準備が必要と判断されることもあります。
このような場合、すぐに転職活動を始めるのではなく、少しずつ働く準備を整えることが重要です。
まずは短時間の仕事や就労支援を活用し、「継続して働ける」実績を作ることで、再びdodaチャレンジを利用できる可能性を高めることができます。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
長期間のブランクがある場合、いきなりフルタイムの仕事を探すのではなく、就労移行支援を活用して働くための準備を進めることが推奨されます。
就労移行支援では、職場でのコミュニケーションや実務経験を積むための訓練を受けることができ、以下のようなメリットがあります。
– 毎日通所することで生活リズムを整えられる
– 実際の業務を想定したトレーニングを受けられる
– 企業実習を通じて「職歴の空白」を埋めることができる
– 就職後のフォローアップも受けられる
特に、「長年働いていなかったために体力や集中力が続くか不安」「職場でのコミュニケーションに自信がない」といった方にとって、就労移行支援はスムーズな職場復帰のための良い準備になります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
いきなりフルタイムの仕事を目指すのが難しい場合は、短時間のアルバイトや在宅ワークを始めて、職歴を作ることも有効な方法です。
たとえば、以下のような形で少しずつ働き始めることで、「安定して働ける」という実績を作ることができます。
– 週1〜2日の短時間バイトからスタートする(コンビニ、事務補助、軽作業など)
– クラウドソーシングでライティングやデータ入力の仕事を始める(自宅で無理なく続けられる)
– フルタイムではなく、週3日勤務の仕事を探す
このように、無理のない範囲で少しずつ就労経験を積んでおくことで、再びdodaチャレンジに登録したときに「継続して働ける人」と判断され、求人紹介を受けやすくなります。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
企業実習やトライアル雇用を活用することで、実際の職場環境で働く経験を積むこともできます。
特に、長期ブランクがある場合、「実際に働けるかどうか不安」と思われやすいため、短期間の実習やトライアルを経験しておくと、企業に対してアピールしやすくなります。
– ハローワークのトライアル雇用制度を利用し、短期間の仕事から始める
– 障がい者就労支援センターなどが紹介する企業実習に参加する
– ボランティア活動や短期のインターンシップで実績を作る
このような経験を積むことで、履歴書や面接で「ブランクがあるけれど、最近は○○の仕事を経験しました」と具体的に説明できるようになります。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方在住の場合、通勤圏内に障がい者雇用の求人が少ないことが原因で、dodaチャレンジでの紹介が難しくなることがあります。
また、フルリモート勤務を希望する場合も、求人が限られるため、紹介を受けられないケースがあります。
このような場合、dodaチャレンジ以外の選択肢も活用しながら、働く環境を見つけていくことが重要です。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
dodaチャレンジ以外にも、障がい者向けに在宅勤務の求人を紹介しているエージェントがあります。
例えば、以下のサービスを活用することで、リモートワークに適した求人を探すことができます。
– atGP在宅ワーク(在宅勤務向けの障がい者求人を多数掲載)
– サーナ(障がい者向けの転職支援サービスで、在宅勤務求人も取り扱いあり)
– ミラトレ(リモートワークや柔軟な働き方に対応した求人を紹介)
これらのエージェントと併用することで、希望に合う求人を見つけられる可能性が高まります。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
フルリモートの求人が見つからない場合は、クラウドソーシングを活用して、在宅でできる仕事の実績を作ることも有効です。
例えば、以下のような仕事に挑戦してみるとよいでしょう。
– ライティング(記事作成、ブログ執筆など)
– データ入力・文字起こし
– 画像加工・デザイン制作
これらの仕事を経験しておくことで、「リモートワークでの業務経験あり」とアピールでき、企業の在宅勤務求人にも応募しやすくなります。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方の求人は、大手の転職エージェントよりも、地元の障がい者就労支援センターやハローワークの方が情報を持っていることがあります。
地域密着型の企業が、ハローワーク経由で障がい者雇用を行っているケースもあるため、地元の支援機関に相談することで、思わぬ求人が見つかる可能性があります。
地方在住の場合は、エージェントだけに頼らず、さまざまな方法で求人情報を収集することが大切です。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
dodaチャレンジで求人紹介を断られる理由の一つに、「希望条件が厳しすぎる」ことがあります。
例えば、「完全在宅勤務」「週3日勤務」「年収○万円以上」「特定の職種のみ希望」など、条件を細かく設定しすぎると、それに合致する求人がほとんどなくなり、結果的に「ご紹介できる求人がありません」と言われてしまうことがあります。
もちろん、働く上で譲れない条件があることは大切ですが、すべての条件を満たす求人を探すのは現実的に難しい場合もあります。
そのため、対処法としては、条件の優先順位を整理し、段階的に理想の働き方に近づける戦略を立てることが重要です。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
まず、希望条件を「絶対に譲れない条件」と「できれば希望したい条件」に分けて整理しましょう。
例えば、以下のように考えると、求人の選択肢を増やしながら、自分の理想に近い仕事を探すことができます。
– 絶対に譲れない条件
– 体調管理のため、フルタイムではなく短時間勤務を希望
– 通勤が難しいため、リモートワークを優先したい
– 業務内容が過去の経験やスキルに合ったもの
– できれば希望したい条件
– 完全在宅勤務が理想だが、一部出社なら対応可能
– 週3日勤務が希望だが、週4日までなら調整可能
– 年収○万円以上が理想だが、まずは経験を積んでからステップアップを目指す
このように、条件を整理することで、求人の幅を広げながら、自分の働きやすい環境を見つけやすくなります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
求人紹介を断られた場合、一度アドバイザーと相談し、譲歩できる条件を見直して再提示するのも有効な方法です。
例えば、以下のように条件を少し緩めるだけで、紹介可能な求人の幅が広がることがあります。
– 「完全在宅勤務」→「週1〜2回の出社なら可能」に変更
– 「週3日勤務」→「週4日勤務も検討」に変更
– 「年収○万円以上」→「まずは現状維持で、昇給の可能性がある企業を探す」に変更
企業側も、柔軟に働ける人材を求めているため、ある程度の譲歩をすることで、選考がスムーズに進む可能性が高まります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
希望条件が厳しい場合、「最初から理想の仕事を探す」のではなく、「まずは経験を積みながら、理想の働き方に近づける」という戦略を立てることも重要です。
例えば、以下のようなキャリアプランを考えることで、無理なく理想の働き方を実現できる可能性が高まります。
1. 最初は条件を少し緩めた求人でスタート
– 週3勤務が理想だが、最初は週4勤務の仕事を選ぶ
– 年収○万円以上が希望だが、まずは経験を積んで昇給を狙う
2. 仕事をしながらスキルアップを図る
– 在宅勤務が可能な仕事に転職し、PCスキルを磨く
– 事務職を希望する場合、Excelや簿記の資格を取得する
3. 経験と実績を積んだ上で、より条件の良い転職先を探す
– 一定期間働いた後、キャリアアップのために再転職を検討する
– フリーランスや業務委託など、新しい働き方を視野に入れる
このように、段階的にキャリアを積みながら、最終的に理想の働き方を実現するというアプローチを取ることで、無理なく転職活動を進めることができます。
転職活動は、一度で理想の仕事を見つけるのが難しいこともありますが、少しずつ経験を積んでいくことで、より良い条件での就職につなげることが可能です。
焦らずに、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジは、障がい者手帳を持っている方を対象とした転職支援サービスのため、手帳未取得の場合は求人紹介を断られることがあります。
また、精神障がいや発達障がいの場合、自治体や医師の判断によって手帳の取得が難航し、結果的に転職活動がスムーズに進まないこともあります。
しかし、手帳がなくても就職の道が完全に閉ざされるわけではありません。
手帳を取得するための手続きを進める、または手帳なしでも応募できる求人を探すことで、転職の選択肢を広げることが可能です。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
障がい者雇用枠の求人は、法律上「障がい者手帳を持っている人」が対象となることが多いため、手帳未取得の状態では応募できる求人が限られてしまいます。
そのため、まずは手帳の取得が可能かどうか、主治医や自治体に相談することが重要です。
精神障がいや発達障がいの場合でも、診断書や自治体の審査を経て手帳を取得できるケースがあります。
手帳の交付基準は自治体ごとに異なるため、まずは役所の福祉窓口で相談し、必要な手続きや申請方法を確認することが大切です。
身体障がいの場合は、障がいの程度によって手帳が交付されるかどうかが異なるため、病院で診断を受けた上で、自治体の基準に沿って申請を進める必要があります。
また、自治体によっては、一定の条件を満たせば福祉サービスを受けられる「受給者証」などの制度があり、手帳がなくても何らかの支援を受けられることがあります。
手帳取得を目指す場合は、早めに主治医や自治体と相談し、スムーズに手続きを進められるよう準備するとよいでしょう。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳の取得が難しい場合でも、手帳なしで応募できる求人を探す方法はあります。
ハローワークでは、障がい者雇用枠ではないものの、障がいへの配慮が可能な企業の求人を紹介してもらえることがあります。
一般枠の求人の中には、障がいを持つ方でも働きやすい環境を整えている企業もあるため、ハローワークの職員と相談しながら、適した求人を探してみるのも一つの方法です。
また、就労移行支援を活用することで、一定期間の職業訓練を受けながら、最終的に手帳なしでも働ける企業を探すことが可能です。
就労移行支援では、PCスキルの習得や実際の業務を想定したトレーニングを受けることができ、職場実習の機会も提供されるため、働く準備を整えることができます。
こうした支援を活用しながら、まずは一般枠での就職を目指し、後に手帳を取得したタイミングで再びdodaチャレンジを利用するという選択肢も考えられます。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
手帳の取得が難しい場合、無理に転職活動を進めるのではなく、まずは体調管理や治療を優先することも重要です。
特に、精神障がいや発達障がいの場合、働く環境によって体調が大きく左右されることがあるため、無理に就職を急ぐと、結果的に職場でのストレスが増え、体調を崩してしまうリスクがあります。
主治医と相談しながら、現時点での働く準備が整っているかを確認し、もし体調が安定していない場合は、まずは治療に専念することを優先しましょう。
手帳の取得が必要な場合も、医師の診断書が求められることが多いため、定期的な診察を受けながら、手帳申請の準備を進めることができます。
手帳を取得した後であれば、再びdodaチャレンジに登録し、より多くの求人を紹介してもらえる可能性が高まります。
転職を成功させるためには、焦らずに自分の状態を整えながら、最適なタイミングで動くことが大切です。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジで求人紹介を断られた場合でも、他の転職支援サービスを活用することで、希望に合った仕事を見つけられる可能性があります。
特に、障がいの種類や求める働き方によって適したサービスが異なるため、自分に合った選択肢を探すことが重要です。
障がい者雇用の転職支援サービスとしては、「アットジーピー(atGP)」「サーナ」「ランスタッド チャレンジド」などがあります。
これらのサービスは、dodaチャレンジと同様に障がい者雇用枠の求人を紹介しており、企業とのマッチングをサポートしてくれます。
特に、「在宅勤務の求人を探している」「一般雇用枠でも挑戦したい」といった場合には、複数のサービスを併用することで、より多くの選択肢を得ることができます。
また、ハローワークの障がい者専門窓口を活用するのも有効な方法です。
ハローワークでは、地域に密着した求人情報を提供しており、地元企業の障がい者雇用枠の求人を紹介してもらえることがあります。
さらに、障がい者就労支援センターでは、実際の職場実習や職業訓練を受けながら就職活動を進めることが可能です。
転職活動が難航している場合は、一度キャリアの方向性を見直し、スキルアップのために職業訓練や就労移行支援を活用するのもよいでしょう。
パソコンスキルの習得や資格取得を目指すことで、応募できる求人の幅が広がり、転職成功の可能性が高まります。
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します
精神障がいや発達障がいを持つ求職者の中には、「dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった」「希望する仕事が見つからなかった」と感じる人も少なくありません。
しかし、精神障がいや発達障がいがあると必ずしも紹介が難しくなるわけではなく、いくつかのポイントを押さえることで転職成功の可能性を高めることができます。
精神障がい・発達障がいの場合、企業側が「どのような配慮をすればよいのか分からない」と判断し、採用を慎重に進めるケースがあります。
そのため、応募時には自分の障がい特性や必要な配慮について具体的に伝えられるように準備しておくことが重要です。
たとえば、「集中力を維持するために短時間勤務を希望する」「口頭指示よりも書面での指示の方が理解しやすい」など、具体的な配慮事項を説明できると、企業側も採用を前向きに検討しやすくなります。
また、精神障がいや発達障がいを持つ求職者向けの特化型サービスを利用するのも有効な方法です。
たとえば、発達障がいや精神障がいのある人向けに特化した「atGP」や「リタリコワークス」などのサービスでは、求職者の特性に合わせた求人を紹介してくれるため、自分に合った職場を見つけやすくなります。
転職活動を進める上で重要なのは、焦らずに自分のペースで準備を整えることです。
必要に応じて、就労移行支援やカウンセリングを活用しながら、少しずつ働く準備を進めていきましょう。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障がい者手帳を持っている方の就職事情は、障がいの程度や業務への影響度によって大きく異なります。
一般的に、企業側が必要な配慮を行いやすいことから、身体障がい者の就職は比較的スムーズに進むことが多いですが、特定の制約がある場合は求人の選択肢が限られることもあります。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障がいの等級が比較的軽度で、業務遂行に大きな支障がない場合は、企業側も安心して採用しやすくなります。
特に、通勤や業務遂行に支障が少ない場合は、一般雇用枠での就職も可能なケースが多く、選択肢が広がる傾向にあります。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
身体障がい者の場合、障がいの特性が企業側にとって理解しやすく、どのような配慮が必要なのかが明確になりやすいことから、採用がスムーズに進むことがあります。
たとえば、車いす利用者にはバリアフリーのオフィスを用意したり、重い荷物を持つ作業を免除するなど、具体的な対応策を企業が検討しやすいのが特徴です。
企業側が合理的配慮を明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
身体障がい者の場合、企業側がどのような配慮を行えばよいのかを具体的に把握しやすいため、合理的配慮を提供しやすくなります。
たとえば、エレベーターの設置や作業内容の調整など、比較的明確な対策を講じることができるため、企業側も安心して採用できるケースが多いです。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
一方で、上肢や下肢に障がいがある場合、通勤や業務遂行に制約があるため、求人の選択肢が狭まることもあります。
特に、車いす利用者の場合、通勤ルートやオフィス環境が適していないと就職が難しくなることがあります。
そのため、在宅勤務が可能な求人を探したり、バリアフリー対応の職場を選ぶことが重要です。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、コミュニケーションに問題がない場合は、一般職種への採用も比較的多くなります。
特に、接客業や事務職など、人とのやり取りが多い職種では、障がいの内容が業務に大きく影響しないことから、積極的に採用されるケースもあります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がい者の中でも、特にPCを使用する業務や事務職の求人は多く、スキルを身につけることで就職の選択肢が広がります。
PCスキルを習得し、資格を取得することで、より安定した職場で働くチャンスを増やすことが可能です。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を持つ方の就職事情は、企業側の理解度や受け入れ態勢によって大きく左右されることがあります。
精神障がいは外見からは分かりにくいため、企業側がどのように配慮すればよいのか判断しにくく、不安を感じるケースも少なくありません。
そのため、求職者自身が自分の特性や必要な配慮を適切に伝えられるかどうかが、就職成功の鍵となります。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障がい者の就職では、症状が安定しており、職場で継続的に働けることが重視される傾向があります。
特に、過去の職歴において安定した勤務経験があるかどうかは、採用の際に重要視されるポイントの一つとなります。
企業側は、採用後に安定して働けるかどうかを見極めようとするため、服薬や通院をしながら安定した生活を送れているか、体調管理の方法を理解しているかといった点が評価の対象になります。
職場での継続勤務のしやすさをアピールするためには、過去の勤務経験の中でどのように仕事を続けられたのかを具体的に説明し、企業側に安心感を与えることが大切です。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいは、身体障がいと異なり外見からは分かりにくいため、企業側が「どのように対応すればよいのか分からない」と感じることが少なくありません。
そのため、採用に慎重になる企業も多く、障がいの特性や必要な配慮が明確でない場合は、選考を通過しにくくなることがあります。
企業側の不安を軽減するためには、求職者自身が自分の障がいの特性を理解し、どのような配慮があれば安定して働けるのかを具体的に伝えることが重要です。
たとえば、静かな環境での作業が必要である場合は、できるだけ人の出入りが少ない部署や席の配置について相談することができます。
また、ストレスの影響を受けやすい場合は、定期的な休憩が必要であることを伝え、どのような頻度で休憩を取ると仕事の効率が保てるのかを説明することも有効です。
企業側に「何をすれば働きやすいのか」が明確に伝わることで、採用の可能性を高めることができます。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
精神障がい者の採用面接では、必要な配慮事項をどのように伝えるかが非常に重要になります。
企業側は、求職者がどのような業務に適しているのか、どのような環境であれば能力を発揮できるのかを知りたいと考えているため、あらかじめ自分の特性や働き方について整理し、分かりやすく説明できるように準備しておくことが求められます。
配慮事項を伝える際には、「業務に支障が出る可能性がある点」と「そのために必要な配慮」をセットで説明すると、企業側も具体的な対応をイメージしやすくなります。
たとえば、集中力が続きにくい特性がある場合は、「1時間ごとに5分程度の休憩を取ることで、作業効率を維持できる」といった形で伝えることで、企業も配慮の内容を理解しやすくなります。
また、通院が必要な場合は、「月に1回、午前中に通院のための時間をいただけると助かりますが、その際は業務の調整を行います」といった形で伝えることで、企業側の不安を軽減することができます。
精神障がい者の就職活動では、企業に対して「障がいがあるから特別な配慮が必要」と一方的に伝えるのではなく、「このような配慮があれば、長く安定して働くことができる」という前向きな姿勢を示すことが大切です。
そうすることで、企業側も採用後の対応をイメージしやすくなり、求職者に対してより良い雇用環境を提供しようと考えるようになります。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳(知的障害者手帳)を持つ方の就職事情は、手帳の区分によって大きく異なります。
療育手帳は、知的障がいの程度に応じて「A判定(重度)」と「B判定(中軽度)」の2つに分類されており、それぞれの区分によって就労の選択肢や支援の内容が変わります。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳を持っている方が働く場合、その区分によって適した就労の形が異なります。
A判定(重度)の場合は、一般就労が難しく、福祉的就労が中心になります。
一方で、B判定(中軽度)の場合は、一般企業での就労も視野に入れることが可能になります。
企業の採用基準や職場環境によって、どのような働き方ができるかが変わるため、まずは自分の特性に合った職種や支援を受けられる就職先を探すことが重要です。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定(重度)の方の場合、企業での一般就労は難しいことが多いため、就労継続支援B型などの福祉的就労を利用するケースが多くなります。
就労継続支援B型では、障がいの特性に合わせた作業を行いながら、職業スキルを習得し、就労の準備を進めることができます。
給与面では一般就労よりも低くなるものの、体調や障がいの状況に応じた働き方が可能なため、無理なく働くことができます。
また、A判定の方でも、障がい者枠のある企業で簡単な軽作業や補助業務を担当するケースもあります。
ただし、その場合でも職場の環境や仕事内容が本人の特性に合っているかどうかをしっかり確認することが大切です。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入れながら就職活動を進めることができます。
特に、障がい者雇用枠を利用することで、事務補助、軽作業、清掃、製造業務などの職種に就くことが可能です。
知的障がいがあっても、業務の手順が明確で、サポート体制が整っている職場であれば、安定して働くことができます。
また、B判定の方の中には、一定の職業スキルを持ち、職業訓練や就労支援を受けることで、一般雇用枠での就労を目指せるケースもあります。
ハローワークの障がい者専門窓口や、就労移行支援を活用しながら、自分に合った働き方を探すことが重要です。
障害の種類と就職難易度について
障がいの種類によって、就職のしやすさや職種の選択肢が異なります。
知的障がいの場合は、業務の手順が明確で、サポート体制が整っている職場での就労が比較的進めやすいとされていますが、専門的なスキルを要する職種への応募は難しいことが多いです。
一方で、精神障がいや発達障がいの場合、知的能力に問題がないケースが多いため、事務職やIT系などの職種での就労が可能な場合もあります。
しかし、障がいの特性によっては対人関係の負担が大きくなることもあるため、職場の環境や業務内容を慎重に選ぶ必要があります。
また、身体障がい者の場合は、障がいの部位や程度によって就職難易度が変わります。
通勤や作業に支障が少ない場合は一般雇用枠での就労も可能ですが、移動や作業の制限がある場合は、在宅勤務や特定の業務に限定されることもあります。
それぞれの障がいに応じた働き方を見つけるためには、自分の特性や強みを理解し、適切な支援を受けながら就職活動を進めることが大切です。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
障害者雇用枠と一般雇用枠は、採用基準や働く環境、企業側の対応において大きな違いがあります。
障害者雇用枠は、障害者雇用促進法に基づき、一定割合の障がい者を雇用することが義務付けられた枠組みであり、障がいに応じた合理的配慮を受けながら働くことが可能です。
一方、一般雇用枠は、障がいの有無を問わず、すべての応募者が同じ基準で採用される枠であり、特別な配慮を受けることなく働くことが前提となります。
どちらの枠で就職するかは、障がいの程度や必要な配慮の内容、職業スキルや経験によって変わります。
障がい者雇用枠では、障がいをオープンにし、適切な配慮を受けながら働くことができるため、継続的な就業を希望する方にとっては大きなメリットがあります。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、企業が障害者雇用促進法に基づき設定している特別な採用枠です。
法律では、一定規模以上の企業に対して障がい者の雇用を義務付けており、企業は法定雇用率を満たすために障害者雇用枠を設けています。
この枠では、障がいの特性に配慮した職務内容が設定され、働きやすい環境が整えられているのが特徴です。
この枠での雇用では、応募者が自身の障がいについてオープンにし、企業がその特性を理解した上で適切な配慮を行うことが前提となっています。
そのため、障がいに伴う制約を抱えながらも、安定して働き続けたいと考えている方に適した雇用形態と言えます。
例えば、体調に応じた勤務時間の調整や、通院のためのスケジュール配慮、業務内容の調整などが行われるケースが多く、働きやすい職場環境が提供されやすいのがメリットです。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
障害者雇用促進法では、一定規模以上の企業に対して障がい者の雇用を義務付けています。
2024年4月からは、この法定雇用率が2.5%に引き上げられるため、今後さらに多くの企業が障がい者を雇用する必要が出てきます。
この法改正により、企業は障害者雇用枠の求人を増やす傾向にあり、求職者にとっては選択肢が広がる可能性があります。
企業は法定雇用率を満たさない場合、納付金を支払う義務があるため、積極的に障がい者雇用を推進する必要があります。
そのため、今後は大企業だけでなく、中小企業でも障害者雇用が進められ、より多様な業務内容や勤務形態で働ける機会が増えると考えられます。
特に、リモートワークやフレックスタイム制の導入が進んでいる企業では、障がい者に対する柔軟な働き方が可能になりつつあります。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠で働く場合、採用の時点で自身の障がいを企業に開示する必要があります。
これは、企業が適切な配慮を行い、求職者にとって働きやすい環境を整えるために不可欠なプロセスです。
採用面接では、どのような配慮があれば働きやすいのか、どのような業務が可能なのかを具体的に説明することが求められます。
例えば、「1時間ごとに短い休憩を取ることで集中力を維持できる」「静かな環境で作業することで生産性が向上する」「定期的な通院が必要であるが、事前にスケジュールを調整すれば業務には支障がない」といった形で、自分の障がいに関する情報を整理して伝えると、企業側も採用後の対応をしやすくなります。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠では、障がいの有無にかかわらず、すべての求職者が同じ基準で採用されます。
選考の際には、スキルや経験、適性が重視されるため、障がい者雇用枠と比べると競争が激しくなります。
企業側は、求職者が業務を遂行できるかどうかを重視し、特別な配慮を前提とせずに採用を進めるため、障がいのある方にとってはハードルが高くなる場合があります。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠では、障がいを開示するかどうかは求職者の判断に委ねられます。
オープン就労を選択すると、企業に障がいを伝えた上で採用されるため、一定の配慮を求めることが可能ですが、クローズ就労を選択した場合は、障がいについて企業に知らせることなく働くことになります。
クローズ就労を選択する場合、採用後に障がいに関する配慮を受けることが難しくなるため、事前に業務内容や職場環境を慎重に確認することが重要です。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、障害者雇用枠のような合理的配慮が義務付けられていないため、基本的には特別な措置を受けることが難しいのが現実です。
例えば、勤務時間の調整や通院の配慮などを求めることが難しいケースもあるため、事前に企業の文化やサポート体制を調べることが大切です。
企業によっては、一般雇用枠でも柔軟な対応を行うケースもあるため、自分に合った環境を見極めることが求められます。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障害者雇用の状況は、年代によって異なり、年齢が上がるほど採用の難しさが増す傾向があります。
企業側が求めるスキルや経験、働き方の柔軟性が年代ごとに異なるため、若年層ほど採用されやすく、高年齢層ほど就職活動に苦戦するケースが多くなります。
また、障がいの種類や程度、職務経験の有無によっても採用の難易度が変わるため、一概に年齢だけが影響するわけではありません。
若年層(20代~30代)の場合、ポテンシャル採用や未経験歓迎の求人が比較的多いため、スキルが不足していても、入社後の成長を期待して採用されるケースがあります。
一方、中高年層(40代~50代)になると、即戦力としてのスキルや職務経験が求められるため、未経験分野への転職は難しくなる傾向があります。
また、60代以上の高齢層では、定年制度の関係でフルタイムの求人が減少し、短時間勤務や契約社員・パートなどの選択肢が増えることが特徴です。
障害者雇用の市場は、近年の法改正により、企業が積極的に採用を進める動きが広がっています。
特に、2024年4月から法定雇用率が2.5%に引き上げられるため、今後はより多くの年代の障がい者が採用される機会が増えると予想されます。
ただし、企業側の受け入れ体制や業種によって、年代ごとの採用ハードルは異なるため、自分に合った職種や雇用形態を選ぶことが重要です。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
厚生労働省が発表した「障害者雇用状況報告(2023年版)」によると、日本における障害者雇用は年々増加傾向にあります。
特に、大企業を中心に法定雇用率を達成するための採用活動が活発化しており、障がい者の就業機会が広がっています。
報告によると、障がい者の雇用者数は過去最高を記録しており、企業が障がい者の受け入れを進めていることがわかります。
年代別に見ると、20代~30代の若年層では、障がい者枠の新卒採用や第二新卒向けの求人が増えており、比較的採用されやすい状況にあります。
特に、事務職やIT関連職種では、未経験者向けの研修制度を整えている企業も多く、職業訓練やスキルアップを経て就職するケースが増えています。
一方、40代以降になると、企業側が求めるスキルや経験が厳しくなり、未経験分野への転職が難しくなる傾向があります。
また、50代~60代の求職者については、フルタイム勤務よりも、短時間勤務や契約社員・パートといった働き方が増えています。
企業としても、高年齢層の雇用には慎重になるケースが多く、職種によっては求人数が限られることもあります。
ただし、長年の経験や専門知識を活かせる職種では、一定の需要があり、採用の可能性は十分にあります。
今後の障害者雇用の動向としては、企業が障がい者雇用の多様化を進め、より多くの年代の求職者にチャンスが与えられることが期待されています。
特に、テレワークの普及や職種の多様化が進むことで、年代を問わず働きやすい環境が整っていくと考えられます。
そのため、求職者側も、スキルアップや職務経験の積み重ねを意識しながら、年齢に応じた適切な就職活動を進めることが重要になります。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。
未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。
経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
障害者雇用において、20〜30代の若年層は比較的採用されやすく、求人数も多い傾向にあります。
その理由の一つとして、企業側が若年層を「成長の余地がある人材」として捉え、ポテンシャル採用を積極的に行っている点が挙げられます。
特に、障害者雇用枠の新卒採用や第二新卒向けの求人が増えており、経験が浅くても研修やOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じてスキルを身につけられる環境が整っている企業が多いことが特徴です。
また、若年層向けの求人では、事務職やIT系職種、カスタマーサポート、軽作業など、幅広い業種で募集が行われています。
近年では、テレワークの導入が進んだことで、在宅勤務可能な求人も増えており、身体的な負担を抑えながら働ける環境も整備されています。
これにより、通勤が難しい方や特定の配慮が必要な方でも、より働きやすい選択肢が広がっています。
若年層の強みとして、スキルを伸ばしやすく、企業側も長期的な育成を見込んで採用しやすい点があります。
そのため、求職者側も未経験からのチャレンジを恐れず、職業訓練や資格取得などを活用しながら、自分に合った仕事を探すことが重要です。
特に、PCスキルやビジネスマナーを学ぶことで、応募できる職種の幅が広がり、採用の可能性をさらに高めることができます。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代以降の障害者雇用では、「スキル・経験」が大きな鍵となります。
企業側は、この年代の求職者に対して即戦力を求める傾向が強いため、未経験分野への転職は難しくなりやすいのが現実です。
特に、事務職や技術職などでは、過去の職務経験や専門的なスキルを持っているかどうかが、採用可否を左右する大きなポイントとなります。
40代以上になると、企業は「この人を採用することで、すぐに業務を任せられるか」「社内の環境になじみやすいか」といった点を重視するため、これまでの職歴や実績をしっかりアピールすることが重要になります。
例えば、事務職を希望する場合は、WordやExcelのスキルを証明できる資格(MOS資格など)を取得する、経理職を目指すなら簿記資格を持っていることが評価されることが多いです。
また、IT業界を志望する場合は、基本的なプログラミングスキルやPC操作に慣れていることを証明することが採用の可能性を高めます。
一方で、スキルや経験が不足している場合、40代以降の転職活動はかなり厳しくなることが予想されます。
その場合は、職業訓練や就労移行支援を活用し、新たなスキルを身につけることが必要です。
また、企業実習や短期間のアルバイトを通じて職務経験を積み、再び正社員雇用を目指す方法も選択肢の一つとなります。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上の障害者雇用では、フルタイムの正社員採用が減少し、「短時間勤務」や「特定業務」に限定されるケースが多くなります。
これは、企業側が50代以上の求職者に対して「体力的な負担を考慮する必要がある」「定年が近いため長期的な雇用が難しい」といった理由から、フルタイムではなくパートや契約社員としての採用を検討することが多いためです。
特に、事務職や軽作業、清掃業務などの業種では、50代以上の求職者向けの短時間勤務の求人が多く見られます。
例えば、データ入力業務やアーカイブ整理など、体力をあまり必要としない業務であれば、年齢に関係なく採用される可能性があります。
また、企業側も「週3日勤務」「1日4時間勤務」といった形で、シフトを柔軟に設定できる人材を求める傾向があり、フルタイムで働くことが難しい場合でも、こうした求人を活用することで就職のチャンスを得ることができます。
また、50代以上の求職者にとっては、これまでの職歴や経験を活かせる専門職の求人が有利に働くことがあります。
例えば、管理職経験がある場合は、企業のバックオフィス業務やコンサルティング業務などに応募できる可能性がありますし、長年の製造業務の経験がある場合は、品質管理や検品作業などに活かせる場面もあります。
ただし、未経験分野への転職は若年層と比べると厳しく、採用のハードルが高くなるため、求職活動を進める際には、現実的な選択肢を検討することが求められます。
また、ハローワークや就労移行支援を活用し、職業訓練を受けることで、より多くの求人に応募できるようになるため、年齢に応じたキャリア形成を考えながら転職活動を進めることが大切です。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
dodaチャレンジをはじめとする障がい者向けの就職エージェントには、明確な年齢制限は設けられていません。
しかし、実際には「50代前半まで」がメインターゲット層となるケースが多く、50代後半から60代以上になると、求人紹介が難しくなる傾向があります。
これは、企業側が採用後の長期雇用を前提とするため、年齢が高くなるほど応募できる求人が限られてしまうためです。
若年層(20代~30代)の場合は、ポテンシャル採用が多く、未経験からの就職が可能な求人が豊富にあります。
一方で、40代以降になると、一定のスキルや経験を求められることが増え、特に50代以降では「即戦力としてすぐに業務を遂行できるか」が厳しく判断されるようになります。
そのため、未経験分野への転職を希望する場合は、職業訓練やスキルアップを積極的に行う必要があります。
また、60代以上になると、企業の定年制度や雇用形態の関係で、フルタイムの正社員としての採用は難しくなり、短時間勤務の契約社員やパート勤務といった形での雇用が主流になります。
そのため、就職活動を進める際には、エージェントだけでなく、他の支援機関も併用しながら、幅広い選択肢を検討することが重要です。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジなどの就職エージェントは、障がい者の就職支援を専門としており、年齢にかかわらず登録・利用が可能です。
しかし、実際に紹介される求人の多くは、40代後半から50代前半までの求職者をターゲットにしている傾向があります。
これは、企業側が障がい者雇用を進める際に、ある程度の就業年数を期待するためであり、50代後半以上の求職者に対しては、長期的な雇用の観点から採用を慎重に判断することが多いためです。
また、年齢が高くなるにつれて、企業側は「即戦力としてすぐに業務を遂行できるか」を重視するため、スキルや経験が不足している場合は、紹介できる求人が限られることがあります。
そのため、50代以上の求職者は、スキルアップや職業訓練を活用しながら、できるだけ選択肢を広げて就職活動を進めることが求められます。
特に、事務職や軽作業などの求人では、一定のPCスキルや業務経験があると採用の可能性が高くなります。
dodaチャレンジに登録する際には、年齢に関係なく応募可能な求人を紹介してもらうことができますが、50代後半以上の求職者は、エージェントを利用するだけでなく、他の支援機関も併用しながら、幅広い選択肢を検討することが重要です。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
50代以上の求職者が就職活動を進める際には、dodaチャレンジなどのエージェントだけでなく、ハローワークの障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)を併用することで、より多くの求人情報を得ることができます。
ハローワークでは、地元企業の求人を中心に紹介してもらえるため、特に地方在住の求職者にとっては、有力な選択肢となります。
障がい者職業センターでは、職業訓練や就労支援プログラムを提供しており、スキルアップをしながら就職活動を進めることができます。
また、就職後の職場定着支援も行っているため、長く働き続けるためのサポートを受けることができます。
特に、50代以上の求職者にとっては、一般企業への就職だけでなく、福祉的就労(就労継続支援A型・B型)も選択肢に入れることで、自分に合った働き方を見つけやすくなります。
dodaチャレンジを利用しながら、ハローワークや障がい者職業センターも活用することで、求職活動の幅を広げることができます。
特に、ハローワークでは、年齢に関係なく応募できる求人も多く、企業との面接調整や書類添削などの支援も受けられるため、エージェントだけに頼るのではなく、複数の支援機関を活用することが成功の鍵となります。
dodaチャレンジで断られたときの対処法についてよくある質問
dodaチャレンジを利用する中で、「求人を紹介してもらえなかった」「面談後に連絡がなかった」といったケースに直面することがあります。
こうした状況に不安を感じる方も多いですが、原因を理解し、適切な対処を行うことで、再びチャンスを得ることができます。
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した転職エージェントであり、多くの求職者にとって有益なサービスですが、必ずしも全員に求人を紹介できるわけではありません。
特に、希望条件が厳しい場合や、スキル・経験が不足している場合は、紹介が難しくなることがあります。
また、面談後に連絡がないケースでは、エージェントの選考基準や求人状況が影響している可能性も考えられます。
ここでは、dodaチャレンジでの求職活動に関して、よくある質問とその対処法を紹介します。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの口コミや評判については、利用者の声がさまざまです。
良い口コミとしては、キャリアアドバイザーが親身に相談に乗ってくれることや、企業とのマッチング精度が高いことが挙げられます。
特に、障がいの特性に応じた配慮事項を考慮しながら求人を紹介してくれる点が、多くの利用者から評価されています。
一方で、悪い口コミとしては、「求人を紹介してもらえなかった」「面談後に連絡がなかった」という意見もあります。
これは、希望条件が厳しすぎる、スキルが不足している、または求人の枠が埋まってしまったなどの理由が影響している可能性があります。
こうした場合は、一度キャリアアドバイザーに相談し、条件の見直しやスキルアップの方向性を検討することが重要です。
関連ページ:「dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット」
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合、まずは「なぜ断られたのか」を確認することが大切です。
主な理由としては、希望条件が厳しすぎる、スキル・経験が不足している、または応募可能な求人がないといった点が考えられます。
もし希望条件が厳しすぎる場合は、条件の見直しを行い、企業にとって採用しやすい形に調整することが有効です。
例えば、「完全在宅勤務のみ」「年収○万円以上」「特定の職種のみ」といった制限を緩めることで、紹介可能な求人が増える可能性があります。
スキル不足が理由で断られた場合は、職業訓練や資格取得を検討するのも一つの方法です。
特に、事務職を希望する場合は、ExcelやWordのスキルを証明する資格を取得すると、応募できる求人の幅が広がります。
また、就労移行支援などのサービスを活用し、実際の業務に近い経験を積むことで、再度dodaチャレンジに登録した際に、より多くの求人を紹介してもらえる可能性があります。
また、dodaチャレンジ以外のエージェントや、ハローワークの障がい者窓口を利用するのも選択肢の一つです。
他のサービスと併用することで、より多くの求人情報を得ることができ、自分に合った職場を見つけやすくなります。
関連ページ:「dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談」
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジで面談を受けた後に連絡がない場合、いくつかの理由が考えられます。
まず、面談の結果、紹介できる求人が見つからなかった場合、エージェント側から積極的な連絡がないケースがあります。
これは、求職者の希望条件と求人が合わなかったり、現在のスキルや経験では紹介が難しいと判断されたりした場合に起こることが多いです。
また、エージェント側の業務の都合により、連絡が遅れていることも考えられます。
特に、求職者が多い時期や、企業側の選考状況によっては、すぐに対応できない場合もあります。
この場合は、一度dodaチャレンジに問い合わせて、現在の状況を確認することをおすすめします。
もし、面談後に全く連絡がない場合は、他の転職支援サービスを併用することも検討するとよいでしょう。
ハローワークの障がい者専門窓口や、他の就職エージェント(atGP、ランスタッドなど)を利用することで、より多くの選択肢を得ることができます。
また、面談時の対応を振り返り、改善点がないか見直すことも重要です。
例えば、自分の希望条件を明確に伝えられていたか、障がいの特性や必要な配慮について適切に説明できたかを確認し、次回の面談に活かすことで、より良い結果を得られる可能性が高まります。
関連ページ:「dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由」
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、求職者の障がいの特性や職歴、希望する働き方などを詳しくヒアリングし、それに合った求人を紹介するための準備が行われます。
面談の流れは、事前の登録内容をもとに担当キャリアアドバイザーと1対1で話す形式が一般的で、対面・オンライン・電話のいずれかで実施されます。
最初に、求職者のこれまでの職歴や経験について確認されます。
どのような業界や職種で働いていたか、現在のスキルや資格、過去の仕事での成功体験や困難だったことなどを聞かれることが多いです。
その後、障がいの特性について詳しく話し、どのような配慮が必要かを具体的に伝えます。
例えば、「長時間の立ち仕事が難しい」「静かな環境で作業したい」「定期的な通院が必要」など、働く上で考慮してもらいたい点を明確にすることが大切です。
次に、希望する職種や働き方について話し合います。
フルタイムかパートタイムか、在宅勤務が可能か、勤務地の希望、業務内容の詳細などを具体的に伝えることで、より自分に合った求人を紹介してもらいやすくなります。
また、これまでに転職活動をした経験がある場合は、応募した企業や面接の結果についても聞かれることがあります。
面談の最後には、今後の転職活動の進め方についてアドバイスを受けることができます。
履歴書や職務経歴書の書き方、面接対策、求人の選び方などについて具体的な指導を受けることも可能です。
もし、その場で紹介できる求人がある場合は、応募を進めるかどうかを相談し、エージェントを通じて企業との調整を行ってもらいます。
関連ページ:「dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について」
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がい者のための転職支援サービスで、障がい者雇用枠の求人紹介や、履歴書・職務経歴書の作成サポート、面接対策、企業との調整などを行う総合的な就職支援を提供しています。
運営元は大手転職エージェントdodaを展開するパーソルグループで、豊富な求人情報と専門的なサポートが強みとなっています。
dodaチャレンジの特徴の一つは、専門のキャリアアドバイザーが求職者の障がいの特性や希望に応じた求人を提案してくれる点です。
一般的な求人サイトと異なり、単に求人情報を提供するだけでなく、求職者一人ひとりに合った職場を見つけるために、企業とのマッチングを重視しています。
そのため、業務内容や職場環境の配慮事項についても詳しく確認しながら、適切な求人を紹介してくれます。
また、dodaチャレンジでは、就職活動だけでなく、入社後の定着支援にも力を入れています。
障がい者雇用では、入社後に職場環境が合わず短期間で離職してしまうケースが少なくありません。
そのため、入社後も定期的なフォローアップを行い、職場での悩みや課題について相談できる体制が整っています。
求人の種類としては、事務職、IT職、軽作業、製造業など、幅広い職種を取り扱っており、在宅勤務が可能な求人や時短勤務の求人など、柔軟な働き方に対応した案件もあります。
これにより、求職者の多様なニーズに応じた仕事探しが可能となっています。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジは、原則として「障がい者手帳を持っている人」を対象とした転職支援サービスです。
そのため、手帳を持っていない場合、障がい者雇用枠の求人紹介を受けることが難しくなります。
ただし、手帳の取得手続きを進めている場合や、自治体の診断書がある場合には、個別に相談できるケースもあります。
障がい者雇用枠の求人は、企業が法律に基づいて設定しているため、応募の際に障がい者手帳の提示が求められることが一般的です。
そのため、手帳を持っていない場合は、一般雇用枠の求人を検討するか、手帳を取得した上で再度dodaチャレンジに登録することをおすすめします。
手帳の取得を検討している場合は、まず主治医や自治体の福祉窓口に相談し、取得の可否や申請手続きを確認するとよいでしょう。
特に、精神障がいや発達障がいの場合は、自治体ごとに手帳の取得条件が異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。
また、ハローワークや就労移行支援事業所では、手帳を持っていなくても利用できる就職支援サービスを提供しているため、これらの機関を併用するのも一つの選択肢となります。
関連ページ:「dodaチャレンジは手帳なしで利用できる?障害者手帳は必須!申請中でも利用できます」
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジは、障がい者手帳を持っている方を対象としているため、手帳未取得の方は基本的に登録ができません。
また、障がいの種類によっては、紹介可能な求人が限られる場合もあります。
例えば、重度の身体障がいがあり、通勤や業務の遂行が難しい場合や、医師から「現時点での就労は困難」と診断されている場合は、就職活動を進める前に、リハビリや就労支援プログラムを利用することが推奨されることがあります。
また、知的障がいや精神障がいの場合、就労継続支援A型・B型といった福祉的就労の方が適していると判断されるケースもあります。
このような場合は、dodaチャレンジではなく、ハローワークや障がい者職業センターの支援を受ける方が適していることもあります。
登録できるかどうか分からない場合は、一度dodaチャレンジの窓口に問い合わせ、自分の状況に応じた対応が可能かどうかを確認するとよいでしょう。
場合によっては、他の就職支援機関や、適した職業訓練プログラムを紹介してもらえることもあります。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会(登録解除)したい場合は、担当キャリアアドバイザーに直接連絡するか、dodaチャレンジの公式サイトに記載されている問い合わせ窓口から手続きを行う必要があります。
基本的に、退会手続きは比較的簡単に進めることができますが、退会前にいくつか注意すべきポイントがあります。
まず、退会を希望する場合は、担当アドバイザーに「今後のサポートを終了したい」旨を伝えます。
この際、特別な理由を伝える必要はありませんが、今後の再登録の可能性を考慮して「就職が決まったため」「一旦転職活動を休止したい」など、簡単な理由を伝えておくとスムーズです。
また、求人応募中の企業がある場合は、応募状況の確認や選考辞退の手続きが必要になるため、必ず担当者と相談しましょう。
dodaチャレンジを退会すると、登録情報が削除され、求人紹介やサポートを受けることができなくなります。
一度退会すると、再度利用する際には新規登録が必要になるため、将来的に利用する可能性がある場合は、退会ではなく「一時的な活動休止」としておくのも一つの選択肢です。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、基本的にオンラインまたは電話で受けることができます。
キャリアアドバイザーとの面談は、求職者の状況や希望に応じて柔軟に対応してもらえるため、対面での相談が難しい方でも安心して利用できます。
キャリアカウンセリングでは、これまでの職歴やスキル、希望する働き方などを詳しくヒアリングし、最適な求人を紹介してもらう流れになります。
また、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、応募企業との調整など、転職活動全般に関するアドバイスも受けることが可能です。
また、dodaチャレンジでは、企業の障がい者雇用に関する情報や、職場での配慮事項なども詳しく説明してもらえるため、「自分に合った環境で働きたいが、どのような求人を探せばよいか分からない」といった方にも適しています。
カウンセリングの予約は、dodaチャレンジの公式サイトから申し込むことができるため、興味のある方は公式サイトを確認してみるとよいでしょう。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには明確な年齢制限はありませんが、実際の求人状況を見ると、主な対象者は20代~50代前半の求職者であることが多いです。
これは、企業側が採用後の長期雇用を前提としているため、年齢が高くなるほど選考のハードルが上がる傾向にあるためです。
20代~30代の若年層は、未経験からのチャレンジがしやすく、求人の選択肢も比較的多いですが、40代以降になると、スキルや経験が求められる求人が増えてきます。
50代以上になると、フルタイムの正社員求人は少なくなり、短時間勤務や契約社員・パート勤務といった形での雇用が中心になります。
年齢に関係なく登録自体は可能ですが、50代後半以上の求職者は、dodaチャレンジだけでなく、ハローワークの障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)などの他の支援機関も併用することで、より多くの選択肢を得ることができます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中でもdodaチャレンジのサービスを利用することができます。
むしろ、現在仕事をしていない方にとっては、転職活動をスムーズに進めるためのサポートを受ける絶好の機会となります。
離職中の方がdodaチャレンジを利用するメリットとして、キャリアアドバイザーが求人探しをサポートしてくれる点や、履歴書・職務経歴書の作成支援を受けられる点が挙げられます。
また、面接対策や企業との交渉も代行してもらえるため、一人で転職活動を進めるよりも効率的に就職先を見つけることが可能です。
ただし、離職期間が長くなっている場合は、ブランクの理由や現在のスキルについて説明できるよう準備しておくことが重要です。
企業側は、長期間のブランクがある求職者に対して「仕事への適応ができるか」「継続して働けるか」といった点を懸念することがあるため、面接時には「どのように仕事復帰を考えているか」について具体的に説明できるようにしておきましょう。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは、基本的に転職を希望する障がい者向けのサービスであるため、新卒の学生に対するサポートは限られています。
多くの求人が即戦力を求める中途採用向けであるため、卒業後に本格的な転職活動を始める際に利用する方が適していると言えます。
ただし、学生でも「卒業後の就職活動に向けて情報収集をしたい」「インターンシップやアルバイトの経験を活かして早めに転職活動をスタートしたい」といった場合は、事前に相談することが可能です。
特に、卒業間近の方や既卒の方であれば、dodaチャレンジのキャリアアドバイザーと面談し、求人の紹介を受けられる場合もあります。
学生の方で障がい者雇用枠を活用した就職を希望する場合は、dodaチャレンジだけでなく、ハローワークの「新卒応援ハローワーク」や、大学のキャリアセンター、障がい者向けの就職イベントなどを併用することで、より多くの情報を得ることができます。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較
dodaチャレンジは、多くの障がい者向けの転職希望者に対応しているものの、すべての求職者に対して必ず求人を紹介できるわけではありません。
希望条件が厳しすぎたり、スキルや職歴が不足していたりすると、求人を紹介してもらえないケースがあります。
そのため、dodaチャレンジのみを利用するのではなく、他の障がい者向け就職サービスと併用することで、より多くの選択肢を得られる可能性が高まります。
障がい者向けの就職支援サービスは複数あり、それぞれ特徴が異なります。
例えば、「atGP(アットジーピー)」は、障がい者雇用専門の転職エージェントとして、企業の採用担当者と直接つながる機会が多いのが特徴です。
一方、「LITALICOワークス」は、就職前のスキルアップ支援が充実しており、すぐに就職が難しい人でも利用しやすいサービスとなっています。
また、ハローワークの障がい者窓口では、地域密着型の求人が多く、特に地方での就職を希望する方に適しています。
dodaチャレンジが提供する求人は、比較的スキルや職歴がある方向けのものが多いため、未経験やブランクが長い方にとっては、他の支援機関を併用することでより多くの可能性を広げることができます。
特に、ハローワークや障がい者職業センターでは、就労支援プログラムや職業訓練を提供しているため、スキルを身につけながら就職活動を進めることが可能です。
また、完全在宅勤務を希望する場合、dodaチャレンジで紹介できる求人が少ないことがあるため、「サーナ(Sana)」や「ランスタッド・チャレンジド」など、在宅勤務の求人が充実しているサービスを活用するとよいでしょう。
これらのエージェントは、障がい者向けのリモートワーク求人を多く取り扱っており、通勤が難しい方にとって適した選択肢となります。
dodaチャレンジを利用する際は、まず自分の希望条件とスキルを明確にし、他の障がい者向け就職サービスと比較しながら、自分に合った方法で転職活動を進めることが重要です。
一つのサービスだけに頼るのではなく、複数の支援機関を併用することで、より良い就職先を見つけることができる可能性が高まります。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ
dodaチャレンジは、多くの障がい者向け求職者を支援する転職エージェントですが、すべての人に必ず求人を紹介できるわけではありません。
実際に、「求人を紹介してもらえなかった」「面談後に連絡がなかった」といった経験をした人もいます。
これは、希望条件が厳しすぎる、スキル・経験が不足している、または対象エリアや職種に制限があるといった理由が影響している可能性があります。
特に、完全在宅勤務や高収入を希望する場合、または未経験分野に挑戦したい場合は、紹介される求人が限られることが多いです。
また、ブランクが長い、職歴が短い、障がいの特性により業務に制限がある場合も、エージェント側が「マッチする求人がない」と判断することがあります。
そのため、求人を紹介されなかったからといって「自分には働ける場所がない」と諦めるのではなく、どのように対処すればチャンスを増やせるかを考えることが大切です。
求人を紹介されなかった場合の対処法として、まずはキャリアアドバイザーと相談し、希望条件を調整することが挙げられます。
例えば、「完全在宅勤務のみ」ではなく、「週1回の出社が可能」「通勤圏内で時短勤務を検討」といった形で条件を柔軟にすると、紹介される求人の幅が広がることがあります。
また、スキルが不足していると判断された場合は、ハローワークの職業訓練や就労移行支援を活用し、PCスキルやビジネスマナーを身につけるのも有効です。
また、dodaチャレンジだけに頼るのではなく、他の障がい者向け転職エージェントやハローワーク、障がい者職業センターなどの公的機関を併用することで、より多くの求人情報を得ることができます。
特に、ハローワークの障がい者窓口では、地域密着型の求人が多く、dodaチャレンジで紹介されなかった求人に出会える可能性もあります。
「dodaチャレンジで求人を紹介されなかった」と感じた方の中には、他の方法で就職に成功したケースも多くあります。
自分の強みや希望条件を見直し、柔軟な姿勢で就職活動を進めることが、成功への近道となります。
焦らず、様々な選択肢を検討しながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。